保育原理で出題される「(1)保育所の役割」について、穴埋めで猛特訓するためのページです。
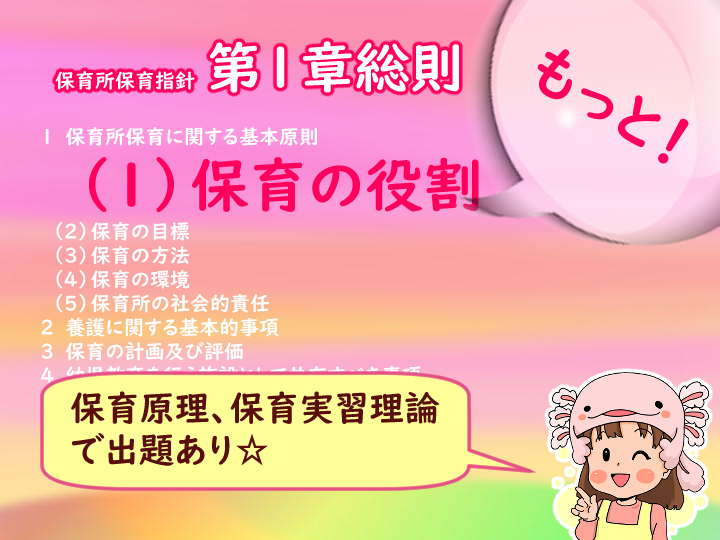
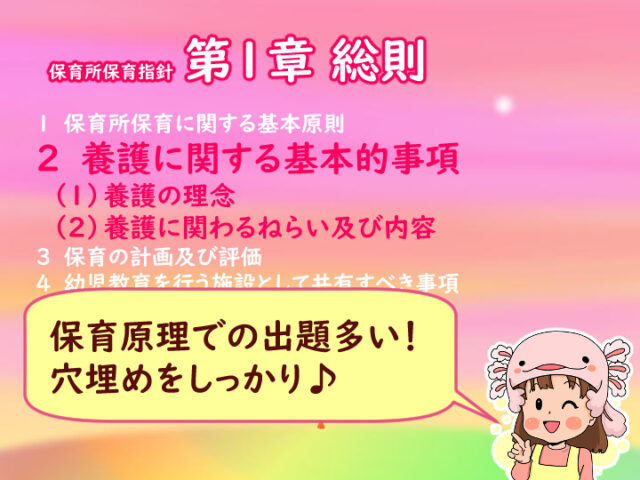 第1章:総則
第1章:総則 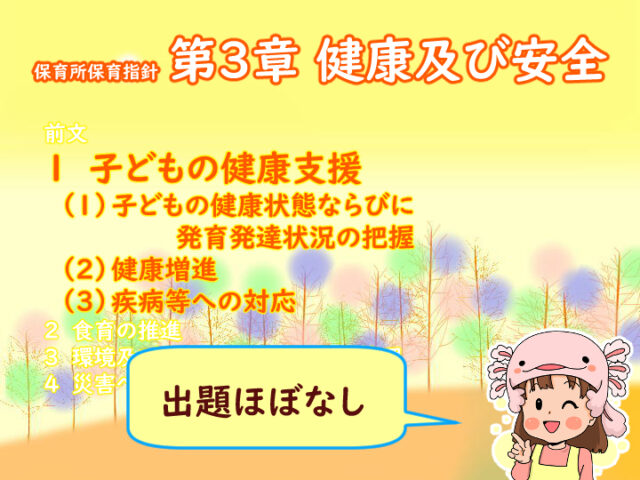 第3章:健康及び安全
第3章:健康及び安全 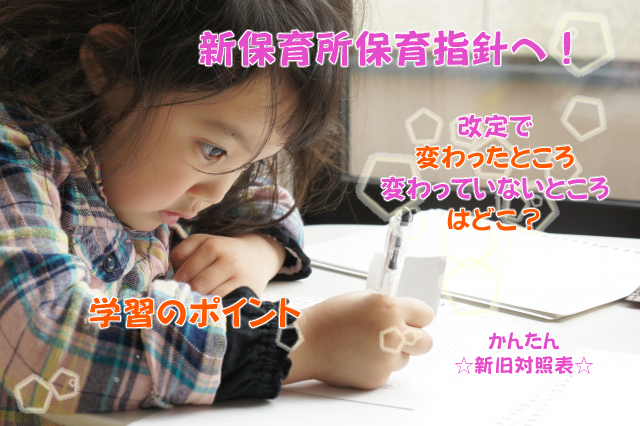 保育士試験
保育士試験 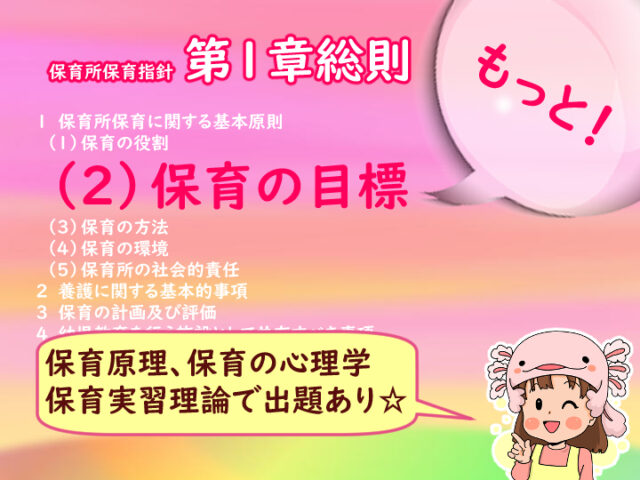 第1章:総則
第1章:総則 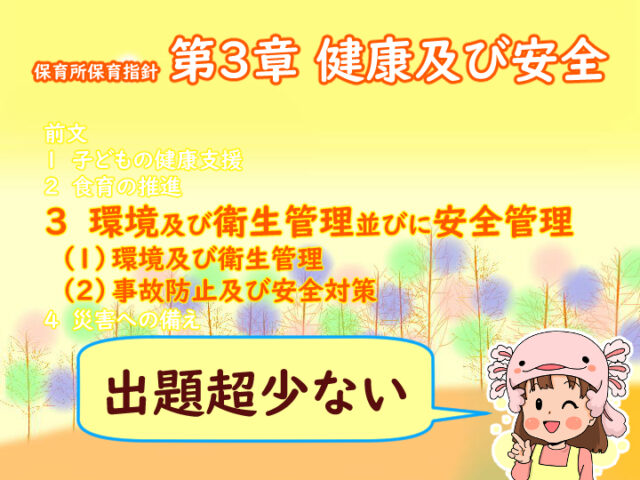 第3章:健康及び安全
第3章:健康及び安全  保育士試験
保育士試験 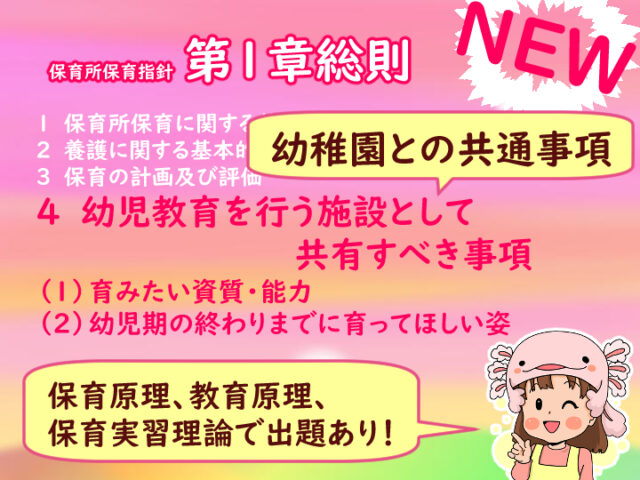 第1章:総則
第1章:総則 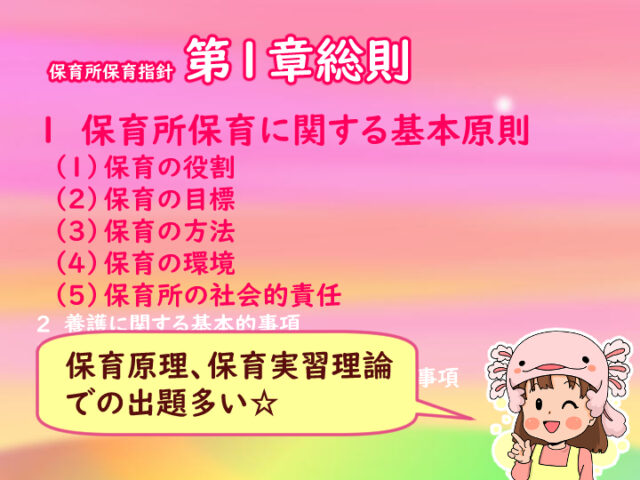 第1章:総則
第1章:総則 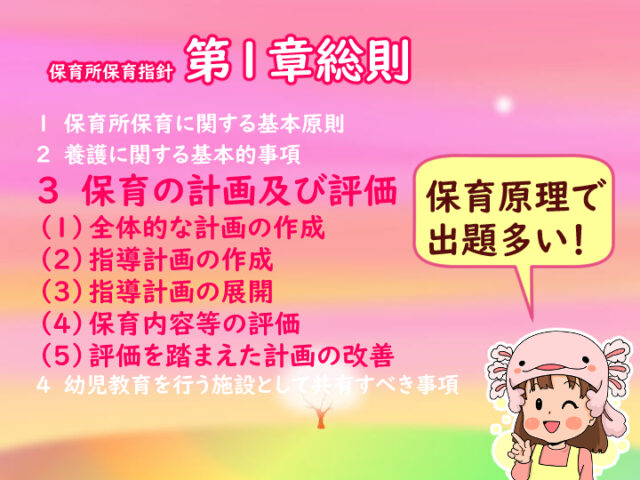 第1章:総則
第1章:総則 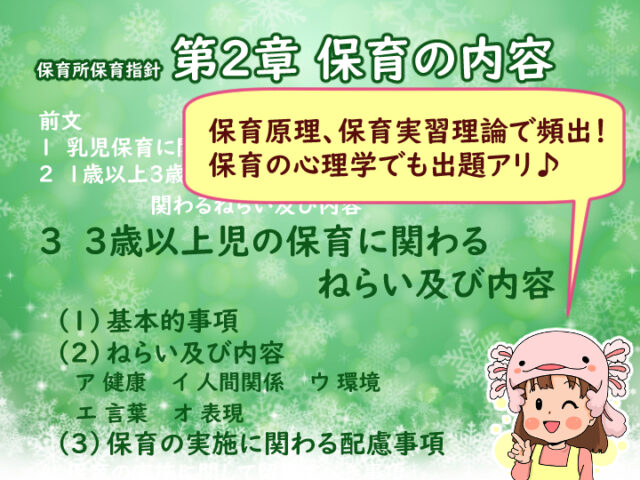 第2章:保育の内容
第2章:保育の内容 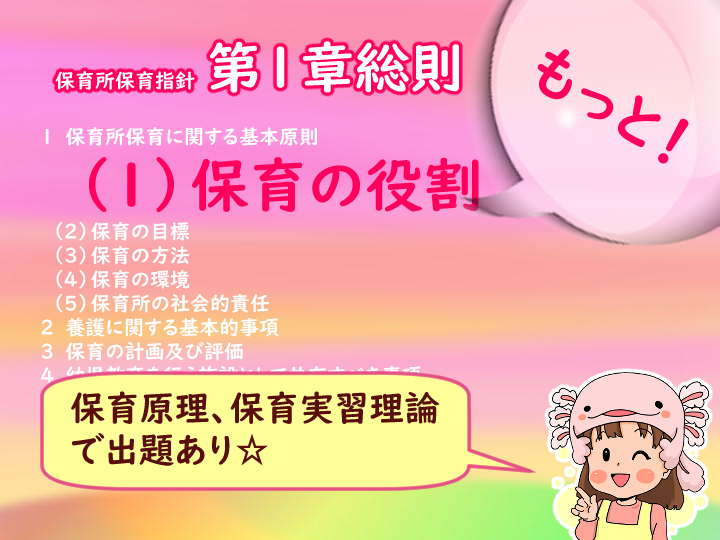 第1章:総則
第1章:総則保育原理で出題される「(1)保育所の役割」について、穴埋めで猛特訓するためのページです。
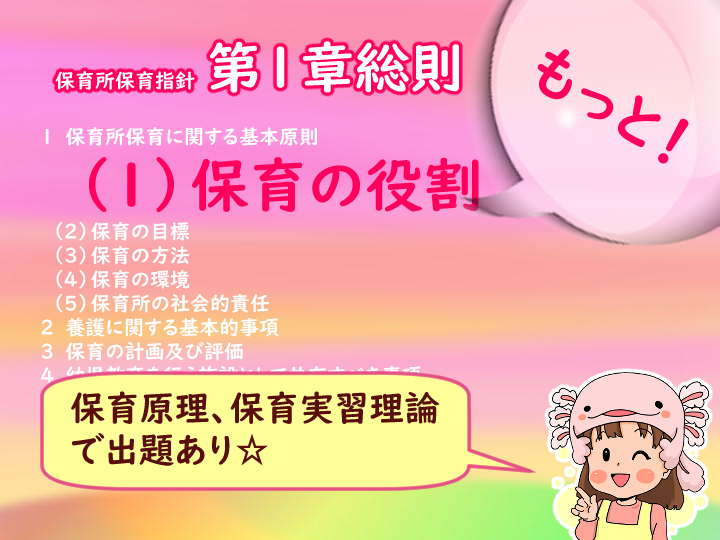
コメント